|
|
釣り雑談コーナーから古くなったものを
こちらに移転しておきます
|
21 竿の切り詰め 気に入った竿だが、少しのことが気になるということがある よく使用している30号/2m40の真鯛竿だが 竿掛けに置こうとすればちょっとのことで部屋の天井につかえてしまう そこで以前、穂先を6cmほど切り詰めた 切り詰め自体は鮎竿でよくやっていたので綺麗にできた そのまま2年ほど使用していたが 小さなボート上ではちょっと長くてとりまわしが意外と不便だ ガイドへの糸絡みの時などだ それに車への収納時には二つ折りにしなければならなく、面倒くさい 私の車は2m10までは折らずに収納できる そこで、2m10以内に切り詰めることにした 竿は穂先を切り詰めると硬くなり 手元近くを切り詰めると調子が変わる 以前から迷っていtのだが、思い切って切り詰めることにした 気が変わるといけないので、金ノコでバット部と元竿を切り離した そして自分の欲しい長さだけ元竿を残して、切り捨てた ノギスで計測したらバット部の太さは9mm、穴は6mm それに比して、切った元竿の太さは6,5mm強で当然入らない そこでバット部の穴を6,5mmのドリルで広げた 真っすぐ広げるのは意外と難しいことは竿造りの経験から知っているが なんとか真っすぐに広げれた 次は切った元竿の尻をここに綺麗に入れなければならない 均一に丸く細くする作業を行います サンドペーパーで少し削り、バット部へ入れて見てまた削るの 地道な作業の繰り返しだ 延々栗返すこと30分 あつらえたようにピッタリと嵌りました このままでも良いのですが、接着剤で固定して終了 非常に気に入った出来上がりとなりました 早く実戦で使用してみたいものです |
|
20 イカラバ 鯛ラバやインチクが流行だが 1個 ¥1,000以上もするものを根掛かりで失うと ショックが大きい 釣りの番組等では釣れたシーンばかり放映しているが こういう仕掛では根掛かりは避けて通れない 私なんかのヘボではなおさらだ 新品を一回投入しただけで、紛失してしまったこともある ならば失っても惜しくないように自作しようと・・ それより何より 自分で作った仕掛で魚を騙すことができれば快感だ  写真下は市販のイカベイト(タコベイトではない)を利用して 作ったものだが、この中に写真上のオモリとハリを仕込んである オモリは7号を使用しているが、深い理由はない 頭(胴)の部分にちょうど収まったからだ ハリは伊勢尼11号2本、ハリスはナイロン4号とした フロロカーボンよりもナイロンの方が絡みがいいのではなかろうかと・・ 一個作るのに5分とかからなかった インチクよりも軽く、全体が柔らかいので 魚が簡単に食い込んでくれるはずと期待しているが、まだ試してない 仕掛が軽いので底を取るのが課題となるが ちょうど良い道具がある アオリイカ釣りのエギング竿とスピニングリールが適当だろう 私のリールにはPE1.5号が100m巻いてある これにフロロの5号程度のリーダーを接続すればピタリだろう 水深30m〜40mぐらいまでなら何とかなりそうだ 釣り方はキジハタやカサゴ等の根魚ならば 底を取ったらその位置でゆっくり上げ下げしてやればいいと思う 鯛ラバやインチクと同じ感覚で使用できるはずだ 鯛ラバが鯛を釣るラバージグなら これはイカの形をしたラバージグなのでイカラバかな・・・ 次はタコベイトを使用したものを製作します 天気が悪くて釣りに行けない時の暇つぶしにはうってつけだ |
|
19 鬼カサゴ餌の短冊 鬼カサゴ狙いではサンマの短冊を多用している 蛍イカの頃を除いてはほとんどだ 他の身餌に比べて食い込みが良いように感じている  上の写真はサンマの背側の短冊と腹身側の短冊だ サンマを三枚におろして、それをまた縦横4等分している 一尾で8枚の餌が出来上がる 背側は青い短冊、腹側は銀色に光る短冊となる どちらもサンマの切り身だからとて同じではない 鬼カサゴは銀色の腹身の方が好きらしい 5年間の統計では、はるかに腹側にぐんぱいが上がる 最初の頃は2本バリにそれぞれ一切づつ付けていたが 近頃は腹側から使い始め、背側は予備餌としている サバの短冊も同じことだろう ただ、サバの場合は斜めに切ることで すべての短冊に銀色部分を含ますことができるが サンマの場合は餌が小さくなってしまうので 斜めに切るのはあまりおもしろくない それと、小さいことですが下部にスリット(切り込み)を入れる方が 鬼カサゴの食いが良くなりますね 毎度、短冊を作るのは面倒臭いのですが 鬼カサゴを食べたさに努力しています |
|
18 極楽孫バリ 我々カートッパーは色々な海域で釣りをする また、色々な状況に応じた仕掛けで釣りをする 呑ませ(泳がせ)釣りにおいても、一本バリ仕掛や孫バリ仕掛けを 生き餌の大きさや種類に応じて使い分けなければならない 当然、一本バリは餌への負担が少なく、泳ぎが良いためアタリが多い でもハリ掛かり率は孫バリ仕掛けに比べて若干落ちる 逆に孫バリはハリ掛かりは良いのだが 餌が弱りやすいという欠点がある 昨年のヒラメ釣りでは豆アジが大きかったので孫バリ仕掛け、 今年は豆アジが小さいので一本バリ仕掛けを多用した 餌の豆アジの大きさは現場で釣ってみないと分からない したがって私は常に2種類の仕掛けを作り、持参していた これでは面倒臭い 全部孫バリ仕掛けで作っておき、餌が小さい時に 切り捨てれば良いのだが、これも不合理だ だいいち、一本バリに比して孫バリ仕掛けは作るのに手間が掛かる 鮎シーズンが終わり、仕掛け入れを整理している時に 極楽背バリを見てピンときた な〜〜んだ! 必要なときだけ孫バリを取り付ければいいんだと・・ ルアーのアシストフックみたいなものを作って持参すればいいんだと・・ それが下の写真で、着脱できる孫バリにしました 名前も鮎仕掛けそのままに、極楽孫バリです   使用方法は孫バリが必要なときに取り出し ハリスにまわし、チチワの中へハリを通して締めて、 元バリで止まるようにすればいいだけです いらなくなったら時間のある人は解き、 面倒臭い人は切り落とせばよい、 もとの一本バリに戻ります また、ハリス上を移動さすことができるので 餌の生きアジの大きさのバラツキにもある程度対応できます 写真は分かりやすいように黒の撚り糸でつくりましたが 透明のナイロンハリスの5、6号でよいと思います 硬いフロロカーボン糸よりはナイロン糸の方が絡みつきがよいでしょう これで海域ごとに作っていた呑ませ釣りの仕掛を 共通させることができました その年ごとに仕掛を作らなくても、作り置きができます |
|
17 逆孫バリ仕掛 今期は呑ませ(泳がせ)釣りに使用する豆アジが小さ過ぎて、 呑み込まれてしまうことが多い 手持ちで釣っていれば問題ではないのだが 私は横着者で、すぐに竿掛けに置きたがる そうすると合わせのタイミングが遅れ、呑み込まれることがままある キジハタやソイ、カサゴといったところならば大事は無い 困るのはヒラメ釣りの場合だ 呑み込まれると、あの鋭い歯で、いとも簡単にハリスを切られる  そこで呑み込まれ対策を考案した 写真は一見、親・孫バリ仕掛けのように見えるが 実は親バリ(チヌ6号)は先端で、上の方が孫バリ(チヌ5号)という 逆の発想だ もちろん豆アジは先端の親バリに、口掛けにする それなら一本バリと同じことで、豆アジの弱りは少ない 根掛かりの危険のリスクはもちろん増大する だが、ヒラメ釣りは根を直撃することは少ないので気にするほどでは無い 油断して呑み込まれた場合、上部に取り付けた孫バリが 活躍してくれるだろうとの淡い期待をしている 先端の親バリ、上部の孫バリの間隔は1センチ5ミリに取ってある これで、横着釣法でもハリスを切られずに取り込めれば儲けものだ |
|
16 移動式ステ糸 我々カートッパーは色んな海域で釣りをする 呑ませ(泳がせ)釣りでは、その海域ごとの仕掛けを作る 根のあらいところではステ糸は短く、平坦なところは長くが常識だ 根の上のキジハタやソイを狙う場合と根際を狙うヒラメ釣りの場合でも ステ糸の長さが違った方が釣り易い 従って、今まで私は両方の仕掛けを作り、持参していた しかしこれでは面倒臭いので、ステ糸を移動式にして 統一することにした 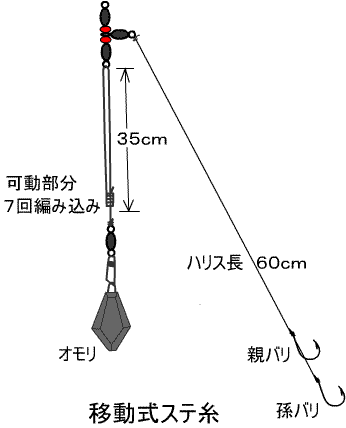 ハリス長を60cmにとるのならば ステ糸を折り返した最短の長さを35cmにとっておけばよい このときハリスはステ糸より25cm長い仕掛けとなり、 根のあらいポイントで使用すればよい また編み込み部分を移動させて、ステ糸の長さを最長にすれば 70cmとなり、ハリスの方が10cm短い仕掛けとなって 根掛かりの少ないポイントで使用すれば棚が取り易くなる |
|
15 ハリのチモト補強 ここのところ、食味優先で夏場はイサキを狙っていた 能登では漁師さんがイサキを専門に狙うことが少ないので 大型が狙えるのだ ところが、真鯛ポイントとイサキポイントは近く、混在している 完全フカセと天秤ズボのコマセ釣りでやっているが 真鯛はフカセ竿に、イサキはズボ竿にというようにうまくは行かぬ ズボ竿に大型真鯛がときたまくる こんな時はたいがい応対が遅れて失敗することが多い ズボ釣りで大型イサキを狙うにはハリス3号程度が最適だろう だが、たまにくる大型真鯛はこれを苦も無く切って行く かといって5号以上を使うとイサキの食いが落ちる 当然、両狙いができる仕掛けが望ましい そこで4号ハリスで、チモトを編みつけて補強することに・・・ 同時にハリもチヌ5号から、チヌ2号(胴打・蛍光・オキアミカラー) へと小さくした  補強方法 まず2号程度の太さのナイロン糸を30cmほど用意する これを4号ハリスに添わせて持つ この2本糸でハリを結ぶ 私の場合はナショナルのハリ結び器を使用してます ここでしっかりと2本同時に締め上げる ハリの下側の余り糸はハリス、ナイロン添え糸共に当然切る ハリのチモト側(上側)のナイロン糸で編みつける できれば上下交互に35〜40回ほど編む 1cmほど編み込んだら、しっかりと結び、ナイロン糸を切る これで補強の編みつけ完了 この仕掛けは、まだシーズン前で使用していません 冬に夏の仕掛け、夏に冬の仕掛けを考えて楽しむのがいいんですよね イメージトレーニングでは大型真鯛が、がっぱ、がっぱなんですが 実戦ではハリが伸ばされそうです・・・ |
|
14 ハリの雑談 底を狙うアマダイ釣りや鬼カサゴ釣りでは根掛かりは避けて通れない まして富山湾においては定置網近辺のポイントが多く 網を止めてある土嚢(ドノウ)やロープにハリが掛かり易い それを無理に引っ張っては、仕掛けごと海中に置きざりにしてしまう これは環境の面からも、決して良いことではない  解決方法 問題は根掛かりをした時にどうやって仕掛けを回収するかだ 上の写真のハリを比較して下さい 上の左はチヌバリ3号、右は5号で、アマダイ釣りに使用しています 下の左はムツバリ16号、右は18号で鬼カサゴ釣りに使用しています 左側が現在私が使用しているもので 右側は数年前に使用していたものです では何故ハリが小さくなっていったのでしょう 小バリが釣れるからではありません ハリが小さくなるごとに軸が細くなるからです 結果、のび易い つまり根掛かり時に、強く引っ張り、ハリを伸ばして外すためです 昔は魚に負けない丈夫なハリを求めて使用していたのですが これは大きな間違いでした 特にアマダイ釣りは飲み込まれることが多いので 細軸のハリに大型が来てもまず大丈夫です 今ではチヌバリ3号に3号ハリスで釣っています 45cm程度のアマダイぐらいまでは平気ですよ 食いを優先させて、ハリス2号に落とすのは意味がありません 3号ハリスだからこそ切れずに、ハリが伸びてくれるのです 伸びたハリを回収したら、ペンチで元の形に戻しましょう そのまま再使用すれば経済的です たったこれだけのことで、仕掛けの消耗が半分以下になります 鬼カサゴ釣りも同じ考えで、ムツバリ16号細軸を使用しており これに4号ハリスの組み合わせで充分です 廉価のハリほど伸び易くて良いですね〜 |
|
13 仕掛け作成器 真鯛狙いのハリスは時には10mを超えることがある 長いと仕掛け作りが結構面倒だ また、エダスを出す時、編みつけも必要だ それにアマダイや鬼カサゴ狙いの時も、常にハリス長が一定なら 棚とりが安定する 仕掛けを作る時に、あると便利この上ないのがこれです 鮎釣りをする釣り人には珍しくもない物だが 私はこれを流用して、海釣りの仕掛け作りに使用している 簡単に作れるので、興味のある方は作ってみて下さい 
写真のものは、2本の支柱の間隔が1.0mで、 ハリスを一巻きすれば、2.0mになるように作成されている (私は間隔50cmで、一巻き1.0mのものと2台持っています) 台には1cm間隔で目盛りがつけてある 二つの支柱に付いているチョウネジは、エダスの編み込み時に 糸をピンと張って止める役目をします ここで注意して欲しいのは、ハリスをはさんだときに ハリスが潰れない素材を選ぶことですね 支柱の高さが右と左で違うのは、糸を斜めに張ることにより 編み込み時に肘が邪魔にならない配慮です ハリスの先端のサルカンやハリはピンで留めればよい 素材の木は何でも良いのですが、若干重さがある方が安定します 釣りから帰ったら、仕掛けを真水に10分ほど浸し その後、この仕掛け作成器に巻き ティシュで水アカをふき取ります そして、ハリを新品に取り替えておけば、次回の釣行も すばやく、楽しくできます |
|
12 豆アジの干物 呑ませ釣りの餌として豆アジを多めに釣ることが多い 沖に行って餌切れは寂しいからだ 持って帰って南蛮漬けにすることもある でも、南蛮漬け一辺倒では飽きが来る したがって、放流してしまうこともよくある 後の処理が面倒だからだ そこで簡単で美味しく食べれるように、丸干しにしましょう 美味でカルシュームが取れるので、一石二鳥ですよ  作成方法 ①豆アジのアゴの部分を三角に切り、エラとワタを取る 鱗なぞはほとんど無いので気にしないで良い 気になる人は刃先で撫でておけばよい ②ボールにタテ塩(海水と同程度の塩分濃度)を作り 45分程度漬ける ③その後、酒に45分漬ける 酒に漬けることによって風味が出、フワリと仕上がる ④キッチンペーパーで酒を拭く ⑤干し網で半日ほど戸外で乾かせば出来上がり 湿度が低く、風のある日が最高 天気が悪い場合はザルに広げて冷蔵庫の中で一日乾かす さっとあぶって頭、骨ごと食する、焦がさないように 病みつきになること請けあいます |
|
11 天秤の作成 真鯛やアジ釣りは中層を釣るので天秤をなくすことは稀だ だが、鬼カサゴやアマダイ釣りではけっこう天秤を失う 定置網近辺やバラ根を攻める関係上、ある程度はやむを得ない ところが以外とこの手の廉価な天秤が釣具店に置いてない 腕長35cm前後になると結構高価なのだ それに自分の希望を満たしたものが少ない それならと、最近は自分に合った天秤を自作している  [自作天秤] 作成方法 ステンレス線が必要なのだが、ホームセンターで販売されて いるステンレスの針金は、ちょっと軟らかく不向きだ すぐ伸びて、形が変わり易いのが理由 ところが或る日、釣具店でうってつけの天秤用針金を見つけた それ以来底物釣りの天秤はすべて自作している 直径1.4mm、長さ50cmのステンレス線が8本入って280円程度 これを加工して作成するのだが、あとは6号程度のタルカン1個と スナップサルカン2個とたこ糸程度の太さの糸があればよい ①まずステンレス線をペンチを使ってこんなふうに折り曲げる  [折り曲げ部分の拡大写真] ②スナップサルカンを一つ入れて、もう一度横に90度折り曲げる  [オモリ取付け部分の作成] ③ペンチで押さえて、縦軸の線を半巻きするように曲げる  [拡大写真] ④これでオモリ取り付け部分は完成  [オモリ取付け部分の拡大写真] ⑤道糸との接続部分はタルカンを通して、たこ糸でとめる 多目に糸を巻いたほうが見栄えが良い 瞬間接着剤を垂らして止める  [道糸との接続部分] ⑥ハリス接続部分はスナップサルカンを通して、たこ糸でとめる 瞬間接着剤を垂らす  [ハリス接続部分] 使用感は思ったより水切れが良く、自分では満足しています 調子に乗って、30本程作ってしまいました |